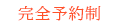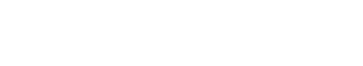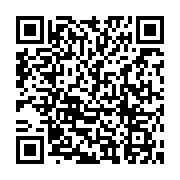鼻詰まり・嗅覚異常について(花粉症・アレルギーは別物で)
風邪などで熱が出ると鼻水が出たり詰まったりします。
鼻粘膜の炎症が起こる現象です。(西洋医学的知見)
私も今回コロナに感染してから多少悩みました。
後遺症で右の鼻が詰まっていたのですが自分で骨格を調整して大分鼻の通りが回復しました。
同時に味覚障害、粘膜、体調を回復させるよう食事やサプリ、稽古で身体を整えるなどの調整が必要でした。
『鼻水が出る仕組み』
・嗅神経は脳に近い → 脳を守る → 鼻水で脳を冷やす
・鼻腔粘膜の炎症部位を冷やす(粘膜の保護)
・ウイルス・細菌・膿を出す解毒作用 → 脳・身体を守る
・嗅覚の保持
温かいものを食べて鼻水が出る現象はおそらく蒸気が鼻粘膜に刺激を与えて脳・粘膜・身体を守ろうとする反応ではないかと思います。
熱い → 冷やす (寒暖差も有)
その他、食べ物が胃に入ると肺(呼吸器)が活性化するという流れもあります。
(東洋医学)
プラスして味覚の機能としても働いていると私はお伝えしています。
『鼻水が溜まる場所』
よく耳にすると思いますが副鼻腔という場所に溜まります。実はこれ前頭洞・篩骨洞・蝶形骨洞・上顎洞(ぜんとうどう・しこつどう・ちょうけいこつどう・じょうがくどう)と4つそれぞれ左右対称にあり総称して副鼻腔と言われます。
解剖学的には副鼻腔炎を起こしやすいのは上顎洞・蝶形骨洞と言われます。
(専門学校時代の教科書記載)
理由は鼻水が出る開口部がやや上方にある(上顎洞)、鼻水が出る開口部が狭い(蝶形骨洞)という理由です。
因みにある医療研究所のデータでは上顎洞、篩骨洞、蝶形骨洞、前頭洞の順で多いという報告もありましたが、私はその人によって違うという見解です。
違いがある理由は後程お書きします。(国立長寿医療研究センターの情報抜粋)
『鼻詰まり・嗅覚異常の原因』
・副鼻腔や鼻粘膜の炎症が強い場合
(排出に追いつかない・腫れていて排水口が狭くなっている)
・頭蓋骨の緊張(様々な理由)
・身体の緊張&歪み
・睡眠時の体勢
・呼吸が浅い
・口呼吸している
(いびきや無呼吸症候群も関係していると思います)
・内臓との関係(東洋医学)
・自律神経のアンバランス(不摂生・疲労・睡眠障害・ストレス)
・食生活の乱れ(早食い・免疫力低下・肥満など)
・精神の不調
・上記の研究センター情報では年齢が高い方、肥満傾向の方、喫煙歴のある方、喘息や慢性気管支炎の既往歴のある方は、そうでない方よりも副鼻腔炎になりやすいことが明らかとあります。その中でも、喘息や慢性気管支炎のある方では、2.7倍から3.8倍ほど副鼻腔炎になりやすく、気管の炎症と副鼻腔炎には密接な関連がある。
このように記載してありますが、私の見解では一つ一つ考えると原因に繋がりますが必ずしもそうでないと思います。
『鼻呼吸をしやすくする施術・鼻水を出す方法・嗅覚を回復させる施術』
以下内容は嗅神経・鼻腔の流れを改善することが目的で整体的な観点です。
自分で出来るケア
・鼻曲げ
鼻をつまんで左右に数秒曲げる(できれば90度くらい)最初は固まっている側に曲げると痛いのですが2~3回程やっていると痛みが和らぎます。
どちらか硬い方がある方は何か原因があります。(西洋医学・東洋医学・両方の観点から)
・耳を引っ張る
耳を引っ張り頭蓋骨を緩める。大体の方が頭蓋骨の緊張が強く、耳だけでは施術が足りないのですが意外とスッキリします。
しかも鼻と耳はとても関係しているので中耳炎に移行しないケアにもなります。
・寝る姿勢の改善や癖の改善
身体も同じですが、どちらかに傾いていると圧迫される方が出てきます。鼻腔に関係している筋肉や骨が偏って固まってしまいます。
頬杖(ほおづえ)、肩肘でテレビを見る、ご自身で原因となりうる癖を探してみてください。
・噛む癖の改善・よく噛む・味わいながら食事をする
いつも硬いものは左右どちらかで噛んでいる場合は噛んでいる方の咀嚼筋が(頚部なども)固まりバランスが悪くなり歪んできます。
噛み癖も顔の歪み、身体の歪みに繋がってしまいます。
とは言え、左右均等にするのは難しいことです。多少はしょうがないことですし、どんなに意識をしていても疲労は溜まってきます。本格的になると嚙み合わせなど歯科治療が必要性になってしまいますので、目だった症状が出ないよう気を付けるくらいにしましょう。
当院の施術ではすぐに症状が戻らないよう患部の施術のみではなく、原因になり得る身体のあらゆるところをチェックして改善のお手伝いをしています。あとアドバイスも。
1カ所が原因で何カ所も患部になってしまうんですね。
・普段から鼻呼吸をする
鼻腔や鼻毛は呼吸や身体を守る意味があります。
体内に入ってくる空気の温度を一定にする・ゴミが入ってこないようにするなど。
しかも普段から鼻呼吸ができていない方は鼻の機能が低下しているため免疫力の低下にも繋がるのではないかと思います。
普段から鼻粘膜が機能していればいつでも活発でいられるものだと思います。
例えば慣れない筋トレをしたら筋肉痛になるようなものです。何回も繰り返すことで筋肉痛も起こらなくなりますよね(笑)
プラス東洋医学では頭寒足熱という言葉がありますが、口呼吸より鼻呼吸の方が脳に近いため脳のオーバーヒートを抑えることができます。
・鼻だけで深呼吸
ポイントは鼻腔の通りを良くしてからやることです。(上記の内容)
・その他いい方法があるのですが見本を見せない分かりずらいので鼻の症状で施術をする際直接お伝えさせていただきますね。
施術では
・頭蓋骨・顔面骨の施術(西洋医学的思考)
反応のいい方はすぐに効果を感じられます。経験上個人差がありますが今回私は1か所1度の施術で9割ほど改善しました。
いくつかポイントがありますが覚えてしまえば簡単です。
因みに施術では細かく頭蓋骨・顔面骨の調整をします。ちょっと難しいのでクライアントさんには施術しながらアドバイスしています。
※効果には個人差めっちゃ有です。経験上その瞬間は比較的良い反応が出ることが正直多いです。しかし、身体の緊張や骨格の歪みが強かったり、内臓の疲労も関係していることが多いので戻りやすいのも事実です。
期間を掛けながらセルフケアや生活の改善、施術を続けていきましょう(^^;)
・身体の調整
鼻の通りを良くしたいと施術に来られる方がいますが、ほとんどの方が身体の歪みがあります。
その原因は様々あり、人によって違うので細かく説明できないのですが、大体の方が骨盤・内臓・経絡の施術で変化が出ます。施術中に鼻が通ったと言われる方は多いです。(反応場所は人それぞれ)
・体調の回復(免疫力)
当たり前ですが免疫力を上げることで炎症や病気を回復させる方法です。
こちらは身体(骨格・筋肉の調整・食生活・私生活・運動・自律神経)、心(心身ともに)を整えることで回復と再発防止を目指します。
上記の原因を分析して改善の努力が必要になりますね。当院では特に自律神経と食生活についてのアドバイスをする事が多いです。
私は今回のコロナ感染後に鼻粘膜の不調と味覚障害もありましたのであるサプリを活用していました。(と言いますか、よく活用しています)
私が考えた雑学的なケア
・鼻をつまんで耳抜きをする感じで空気を鼻洞にいれてから鼻水を出す方法
ティッシュで鼻をつまんで上記を1~2秒やり、すぐに鼻水を出します。
もしかしたらご存じの方もいらっしゃるかもですが、これは炎症で腫れている時でも中々使える方法です。
詳しく思い出せないですが子供のころから使っている方法で、今では娘にも使っています。
・頭を下に傾けてから出す
重力によって鼻水や膿が副鼻腔下部に下がり開口部から出ずらい状態を一度上方へ上げることで出やすくする方法です。
何となく分かってもらえるでしょうか。
コツは頭を上げた瞬間に鼻をかぐことで出やすくなります。
これはサーフィン後に副鼻腔に入った海水を出すために思い付いた方法です。
(おそらく2000年くらいです)
『臨床では教科書と違う』(私の経験上)
解剖学の教科書では上顎洞・蝶形骨洞の順で詰まりやすい。
研究センターでは上顎洞・篩骨洞・蝶形骨洞・前頭洞の順で詰まりやすい。
とありました。
しかし私の経験上、前頭洞・篩骨洞も詰まりやすいと感じます。臨床で実際にそうですし、病院でCT検査をした方がいつもと違う前頭洞に詰まっていたと言われた方もいました。
なぜかを考えると、前頭洞は名前の通り前頭骨(おでこ)にあり、前頭骨にくっつくように篩骨があります。
勘が鋭い方は気付かれたかもですが、
眉間にシワが寄っている方や、パソコン画面などで目を使われている方は前頭骨がめっちゃ硬くなっています。あと身体が前かがみになっている方も。
捕捉しますと、
目の疲労と身体の疲労以外では精神状態も顕著に表れるのも眉間です。
前頭洞に詰まっていた方は眉間に縦のシワがくっきりありました。
前頭骨の中には脳の一部の前頭葉があり情緒・計画・問題解決などの働きをしています。(他にもたくさんの働きが)
いつも怒っている方や考え事をしている方は要注意です。(精神状態・自律神経の緊張)
そんな方は歯ぎしりをしていたり睡眠障害もあります。
ということは人によって眉間にシワが寄っておでこが緊張することで前頭洞や篩骨洞に溜まりやすいという事です。
臨床では違うという理由は(経験上)一部教科書や研究センターの情報を載せましたが、実際に目の前で診た結果という事でした。
そして、このような症状でお悩みの方はセルフケアも必要ですし、中には心の施術が必要な方もいらっしゃいます。
繰り返している方は何か原因があると思います。
『まとめ』
後半はちょっと鼻水の話からずれてしまいましたが…
皆さんはどうでしょう。お悩みの方は原因はありましたか?
この記事が少しでもお役に立てればと思います。
私はコロナで寝込んでいた時に人に貢献することをずっと考えていました。今回の記事もその一つです。
薬や病院での緊急処置は対症療法としてメリットがあると思いますが、根本的な改善になっていないことがほとんどだと思います。
(当院の方針は根本施術・予防施術ですが対症療法の処置が素晴らしいことは重々理解しています)
病院は原因を教えてくれません。今までのクライアントさんから病院で原因を教えてくれたと聞いたことがありません。(耳鼻科に限らず)
いい病院があると聞いたことはありますが対症療法としてです。
ここまでお悩みの方の力になれるよう真剣に書きましたが、自分の力で繰り返さないためにはどうしたらいいでしょうか。
それは原因を知って改善させること・そこに向かって努力することだと私は一番に考えています。その原因とアドバイスをお伝えするのが私の仕事であり、本人の治したいという思いがあって改善に向かいます。
ちょっと厳しいお伝えですが、人任せでは治らないという事をお伝えさせていただきます。
施術後は改善しても戻ってしまう事がよくあります。
初めは多少戻ることは仕方がないことですが、施術・セルフケア・原因である生活の改善を続けることで戻りにくくなり、次第に戻る期間が長くなるものです。慢性的な症状ほど変化が出るまでの期間も掛かります。
その中で生活や間違った身体の使い方に問題がある場合は施術だけでは改善できません。
ほとんどの方が生活の中に原因があったりします。
なので当院では施術も大事ですが問診とアドバイスを特に重視しています。
今回の嗅神経セルフケアの内容は何か人に貢献したいという思いで一般の方でも簡単にできるような内容を考えてお載せしました。
自己分析をして、出来そうなことから試していただきたいと思っています(^^;)
そして、お悩みの方が少しでも興味を持っていただけたら予約のご連絡をいただけたらと思います。
『最後に』
当院の方針は症状の改善と、その後の健康と幸せになるお手伝いです。
幸せのお手伝いとは治ったからそこで終わりではなく、予防施術・セルフケアを続けることが健康に繋がり、幸せに生きられる。そんなお手伝いをさせていただくことです。
この思いは伝え続けていこうと思っています。
こんなことお伝えしながらですが、当院にも対症療法としてご利用くださる方もいらっしゃいます。
それはそれで必要と思ってお越しくださることにとっても感謝しております。
ありがとうございます。
以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。